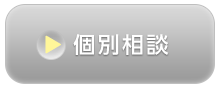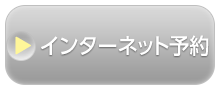インプラントのメンテナンスが大切な理由
2025年5月15日
こんにちは♬
インプラント治療を受けた方の中には、「人工の歯だからむし歯にもならないし、メンテナンスはそれほど必要ないのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実はインプラントこそ治療後のケアが非常に大切なのです。今回は、インプラントのメンテナンスが大切な理由についてご紹介します。

●インプラントで注意すべき病気
インプラントは、顎の骨に人工の根(フィクスチャー)を埋め込み、その上に人工歯を装着する治療です。天然の歯と比べてむし歯になることはありませんが、「インプラント周囲炎」という病気には注意が必要です。
インプラント周囲炎とは、インプラントの周りに炎症が起きる病気で、進行するとインプラントを支える骨が溶けてしまい、最終的には脱落してしまうこともある怖い病気です。症状は歯周病に似ており、最初は歯ぐきが赤く腫れたり、出血したりする程度ですが、痛みが出にくいため気づきにくいのが特徴です。
このインプラント周囲炎の主な原因は、プラーク(歯垢)や歯石の付着です。毎日のセルフケアだけでは落としきれない汚れが少しずつ蓄積し、炎症を引き起こします。
●メンテナンスが大切な理由
インプラントを長持ちさせるためには、「正しいセルフケア」と「歯科医院での定期的なメンテナンス」の両方が不可欠です。
定期的なメンテナンスでは、以下のようなチェックやケアを行います:
・インプラントの周囲に炎症がないかの確認
・専用器具によるプラーク・歯石の除去
・噛み合わせや歯ぐきの状態の確認
・清掃方法の見直し・アドバイス
特にインプラントは天然の歯と違い、免疫のバリア機能が働きにくいため、炎症に対して脆弱です。そのため、定期的なプロのケアで健康な状態を維持することがとても重要なのです。
●まとめ
インプラントはしっかりメンテナンスを続ければ、10年、20年と長く使える頼もしい人工歯です。逆に、ケアを怠ると数年でトラブルが起きてしまうこともあります。
せっかく時間と費用をかけて行った治療ですので、その価値を最大限に引き出すためにも、定期的なメンテナンスの習慣を忘れずに続けていきましょう。
「インプラントを入れてから、少し不安がある」「最近メンテナンスに行けていない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
診療のご予約はお電話やwebにてお待ちしております🦷
歯を失うことで「見えない出費」が生じる!?
2025年5月1日
こんにちは♬
「歯を失うこと」が健康面だけでなく、経済的にも大きな損失につながることをご存知でしょうか?むし歯や歯周病を放置して歯を失ってしまうと、見た目や噛む力の問題だけでなく、医療費や生活の質にも大きな影響を及ぼす可能性があります。今回は、歯を失うことで生じる「見えない出費」についてご紹介します。

●歯の本数が健康に影響する理由
「8020運動(80歳になっても20本以上の歯を保とうという取り組み)」をご存知でしょうか?実はこの8020を達成している高齢者は、達成していない方と比べて入院医療費が約5分の1で済んでいるというデータがあります。つまり、歯が健康な人ほど、医療費が抑えられているのです。
さらに、80歳を対象に行われた調査では、「歯が20本以上ある方」の約80%が自立した日常生活を送れている一方で、「歯が9本以下しかなく、入れ歯も使っていない方」では、自立した生活が送れている方はわずか約20%という結果もあります。この差が生まれる背景には、「噛む力」の重要性が関係しています。
●歯を失うと何が起こる?
歯が少なくなると、食べ物をしっかり噛むことが難しくなり、消化不良を起こしやすくなります。その影響で栄養バランスが崩れやすくなり、免疫力も低下しやすくなってしまいます。
また、噛む力が衰えることで脳への刺激が減り、認知機能の低下や、姿勢のバランスが崩れて歩行障害、転倒リスクの増加などにもつながると考えられています。このような体調の変化が積み重なることで病院への通院や入院が増え、医療費がかさむ原因になってしまうのです。
●歯の健康=身体の健康=生活コストの削減
「歯が1本くらいなくても…」と軽く考えがちですが、実際には1本の歯の役割は非常に大きく、全身の健康を支えているのです。歯がしっかり残っていることでよく噛んで食事ができます。また、体調管理も容易になり、結果的に医療費を抑えられるということが、多くの研究でも明らかになっています。
●まとめ
むし歯や歯周病は、早期に発見し適切に対処すれば、歯を守ることができる病気です。そのためにも、定期的な歯科検診と毎日の丁寧な歯磨きで、予防意識を高めることが大切です。将来の健康と医療費を守るために、今のうちからお口の健康にしっかり向き合ってみましょう。気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
診療のご予約はお電話やwebからお待ちしております🦷
オフィスホワイトニングは1回でどのくらい白くなる?
2025年4月15日
こんにちは♬
オフィスホワイトニングは、歯科医院で行う専門的なホワイトニング治療です。即効性があり短時間で歯を白くできるのが特徴ですが、「1回の施術でどのくらい白くなるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。今回は、オフィスホワイトニングの効果についてご紹介します。

●オフィスホワイトニングの効果
オフィスホワイトニングでは、専用の高濃度ホワイトニング剤を歯に塗布し、特殊な光を当てることで歯の色素を分解します。その結果、1回の施術でおおよそ2段階程度白くなるといわれています。
●「2段階白くなる」とは?
歯の色の明るさは、シェードガイド(歯の色見本)を基準に測定されます。通常、オフィスホワイトニングを1回受けると、このシェードガイドで約2段階明るくなることが一般的です。個人差はありますが、歯の色が少し暗めの方ほど、白さの変化を実感しやすい傾向があります。
●1回で十分な白さになる?
1回のオフィスホワイトニングである程度の白さは実感できますが、理想的な白さに到達するには複数回の処置が必要な場合もあります。特に、もともとの歯の色が濃い方や、コーヒー・紅茶・タバコなどによる着色が強い方は、1回の施術だけでは希望の白さにならないことがあります。
●ホワイトニング効果を長持ちさせるには?
オフィスホワイトニングの効果を持続させるためには、以下のポイントに注意しましょう。
・色の濃い飲食物を控える
ホワイトニング直後の歯は、色を吸収しやすい状態になっています。コーヒー、紅茶、赤ワイン、カレー、醤油などの色の濃い飲食物はできるだけ控えましょう。
・ホームホワイトニングと併用する
より長く白さを維持するために、歯科医院で提供されるホームホワイトニングを併用するのもおすすめです。自宅で定期的にケアすることで、白さをキープしやすくなります。
・定期的なメンテナンスを受ける
オフィスホワイトニングの効果を持続させるために、半年〜1年ごとのメンテナンスを受けるとよいでしょう。歯の着色が気になり始めたら、早めにホワイトニングを行うのが理想です。
●まとめ
オフィスホワイトニングは、1回の施術で約2段階歯を白くすることができます。ただし、理想の白さを目指す場合は、複数回の施術やホームホワイトニングとの併用が必要になることもあります。施術後のケアをしっかり行い、美しい白い歯を長く維持しましょう。
診療のご予約はお電話やwebにてお待ちしております🦷
意外と知らない!唾液の「緩衝能」とは?
2025年4月1日
こんにちは♬
私たちの口の中では、食事や飲み物の影響で酸性やアルカリ性の環境が変化します。その変化を中和し、口腔内のpHバランスを保つ役割を果たすのが唾液の「緩衝能」です。唾液の緩衝能が高いとむし歯や歯周病のリスクが低くなり、口の中の健康が保たれやすくなります。今回は、唾液の緩衝能についてご紹介します。

●唾液の緩衝能の役割
唾液には、食事や飲み物によって酸性に傾いた口腔内を中和し、歯を酸によるダメージから守る働きがあります。
・pHバランスを調整
食事のたびに口の中は酸性に傾きますが、唾液の緩衝能がしっかり働くことで、pHが適切なレベル(中性付近)に戻ります。これにより、歯の表面が溶ける「脱灰」を防ぎ、「再石灰化」を促進することができます。
・むし歯予防
口の中が酸性の状態が続くと、歯の表面が溶けやすくなり、むし歯のリスクが高まります。しかし、唾液の緩衝能が高いと酸をすばやく中和し、歯の健康を保つことができます。
・歯周病予防
歯周病菌は酸性環境を好むため、口腔内のpHバランスが崩れると、歯周病が進行しやすくなります。唾液の緩衝能が高いと細菌の繁殖を抑え、歯周病のリスクを低減することができます。
●唾液の緩衝能を高める方法
唾液の緩衝能には個人差がありますが、日常の習慣によって向上させることが可能です。
・よく噛んで食べる
咀嚼回数を増やすことで、唾液の分泌が促進されます。特に硬めの食品(野菜、ナッツ、噛み応えのある肉類など)を意識的に食べるとよいでしょう。
・水分をしっかり摂る
体内の水分量が不足すると、唾液の分泌が減り、緩衝能も低下します。こまめに水を飲み、脱水を防ぐことが重要です。
・唾液腺マッサージ
耳の前や顎の下にある唾液腺をマッサージすると、唾液の分泌が促進されます。特に口の渇きを感じやすい方にはおすすめです。
・キシリトールを活用
キシリトールは唾液の分泌を促し、むし歯予防にも効果的です。キシリトールガムを噛むことで、緩衝能の向上が期待できます。
・偏った食生活を避ける
糖分の多い食品や酸性の飲み物(炭酸飲料、ジュース、スポーツドリンク)を頻繁に摂ると、唾液の緩衝能が追いつかなくなります。バランスの取れた食事を心がけましょう。
●まとめ
唾液の緩衝能は、口腔内の健康を守る重要な役割を果たしています。pHバランスを調整し、むし歯や歯周病のリスクを低減するため、唾液の分泌を促す生活習慣を意識することが大切です。日々の食事や生活習慣を見直し、健康な口腔環境を維持しましょう!
診療のご予約はお電話やwebからお待ちしております🦷
気になる歯の黄ばみ その原因は?
2025年3月15日
こんにちは♬
ふと鏡を見たときに歯の黄ばみが気になることはありませんか?白い歯は健康的で清潔感がある印象を与えますが、黄ばんでいると気になってしまうものです。実は、歯の黄ばみにはさまざまな原因があります。今回は、歯が黄ばむ主な原因を4つに分けてご紹介します。

●日常の飲食習慣による黄ばみ
最も多い原因は飲食物による着色汚れ(ステイン)です。特定の食べ物や飲み物が歯に色素を付着させ、黄ばみの原因となります。
着色しやすい飲食物の例
・コーヒー・紅茶・緑茶
・赤ワイン
・カレーやトマトソースなど色の濃い調味料
・チョコレート
・タバコのヤニ
これらの食品や嗜好品に含まれる色素が歯の表面に蓄積し、次第に黄ばみが目立つようになります。また、タバコのヤニは特に付着力が強く、通常の歯磨きでは除去しきれないこともあります。
対策としては、色素沈着を防ぐために飲食後すぐに水で口をすすぐことや、定期的なクリーニングを受けることが効果的です。
●加齢による黄ばみ
加齢も歯の黄ばみの大きな原因です。歯はエナメル質という外層で覆われていますが、加齢に伴いこのエナメル質が徐々に薄くなっていきます。エナメル質の下には象牙質と呼ばれる層があり、象牙質は黄色っぽい色をしています。エナメル質が薄くなることで象牙質が透けて見え、結果的に歯が黄ばんで見えるのです。
対策としてはホワイトニングや、エナメル質を強化するフッ素配合の歯磨き粉を使うことが有効です。
●全身疾患や薬剤の影響による変色
歯の変色は、全身疾患や薬剤の影響で起こることもあります。特に有名なのがテトラサイクリン系抗生物質による変色です。テトラサイクリンは、歯が形成される時期(妊娠中や幼少期)に服用すると、歯の内部に色素が沈着し、灰色や茶色っぽい色に変色することがあります。これをテトラサイクリン歯と呼びます。
この場合、一度変色すると通常のホワイトニングでは改善が難しく、ラミネートべニアやセラミック治療などが検討されることもあります。
●遺伝による影響
歯の色には遺伝的な要素もあります。人によってエナメル質の厚さや象牙質の色味が異なり、これが歯の色の違いに影響します。家族で似たような歯の色の場合、遺伝が関与している可能性が高いと言えるでしょう。
遺伝による黄ばみは生活習慣では防ぎづらいですが、ホワイトニング治療や審美歯科の相談を受けることで改善が期待できます。
●まとめ
歯の黄ばみには、飲食習慣、加齢、全身疾患、遺伝といったさまざまな原因があります。それぞれ原因が異なるため、適切な対策も異なります。気になる場合はまずは歯科医院で原因を特定してもらい、原因に応じたケアを行いましょう。
診療のご予約はお電話やwebにてお待ちしております🦷
新年度を迎える前に 歯のクリーニングと検診で口元をリフレッシュ!
2025年3月1日
こんにちは♬
新年度は新しいスタートを切るタイミングです。職場や学校、環境の変化が訪れるこの季節に向けて、気持ちを新たに準備を進めている方も多いのではないでしょうか?その中で、忘れがちなのが歯の健康チェックです。新しい出会いやイベントが増えるこの時期こそ、歯のクリーニングと定期検診を受けて口元をリフレッシュしておきましょう。

●新年度に歯のチェックが必要な理由
1年の始まりや新年度は、生活習慣を見直す良い機会です。歯の検診やクリーニングは、単なるむし歯予防だけでなく、口元の美しさや全身の健康維持にもつながります。
新年度に検診をおすすめする主な理由を3つご紹介します。
・生活習慣の乱れが影響しやすい時期
年度末は仕事や学校の行事が重なり、忙しさから生活習慣が乱れやすくなります。特に、食事や歯磨きがおろそかになりがちな時期は要注意です。気づかないうちに歯石がたまり、初期のむし歯や歯周病が進行している可能性があります。早めにクリーニングを行えば、これらのトラブルを未然に防げます。
・第一印象が大切な場面が増える
新しい環境では、第一印象が重要になります。口元の印象は想像以上に人に影響を与えるものです。歯の黄ばみや口臭は、知らないうちにマイナスな印象を与えることもあります。
・全身の健康チェックにもなる
歯の健康状態は全身の健康と深く関係しています。歯周病は糖尿病や心疾患、脳卒中などのリスクを高めることが分かっています。定期的な検診で歯周病を早期発見・治療することは、健康維持にもつながります。
●歯のクリーニングではどんなことをするの?
歯のクリーニングでは、主に歯科衛生士が専用の器具を使って歯石やステイン(着色汚れ)を除去します。毎日の歯磨きだけでは落としきれない汚れも、プロの手にかかればスッキリきれいになります。
・歯石除去:歯周ポケットにたまった歯石を取り除きます。
・ステイン除去:お茶やコーヒーによる着色汚れをきれいにします。
・フッ素塗布:歯の再石灰化を促進し、むし歯予防効果を高めます。
クリーニング後は歯がツルツルと滑らかになり、口内がさっぱりします。仕上がりを実感できるので、爽快感も得られるでしょう。
●検診とクリーニングをセットで!
検診とクリーニングを同時に受けることで、より効果的な口腔ケアができます。検診ではむし歯や歯周病の早期発見が可能ですし、治療が必要な場合も早めに対処できます。定期的な検診を受けている人は歯を失うリスクが低いというデータがあることからも、3ヶ月~半年に1回を目安に検診を受けましょう。
●まとめ
新年度を迎える前に歯のクリーニングと検診を受けて、口元も気持ちもリフレッシュしましょう!
診療のご予約はお電話やwebからお待ちしております🦷
智歯周囲炎とは?原因や症状、治療法を解説
2025年2月15日
こんにちは♬
智歯(親知らず)は、多くの人にとって問題を引き起こしやすい歯です。その中でも、智歯の周りに炎症が生じる「智歯周囲炎(ちししゅういえん)」は、痛みや腫れ、さらには全身の健康に影響を及ぼすこともあります。
今回は智歯周囲炎の原因や症状、治療法、予防策についてご紹介します🦷

●智歯周囲炎とは?
智歯周囲炎とは、親知らずの周囲の歯ぐきに炎症が生じる疾患です。特に親知らずが完全に生えきらず歯ぐきに覆われている場合や、斜めに生えている場合に発生しやすくなります。この状態では歯と歯ぐきの間に隙間ができ、食べかすや細菌がたまりやすくなるため、炎症が引き起こされるのです。
●智歯周囲炎の主な原因
智歯周囲炎の原因には以下のようなものがあります。
・親知らずの不完全な萌出
親知らずが斜めや横向きに生えている場合、歯ぐきの一部が覆われた状態になります。この部分は清掃が難しく、細菌が繁殖しやすくなります。
・プラークや食べかすの蓄積
親知らず周囲の清掃が不十分だとプラークや食べかすがたまり、炎症の原因となります。
・免疫力の低下
体調不良やストレス、疲労が重なると免疫力が低下し、炎症を起こしやすくなります。
●智歯周囲炎の症状
智歯周囲炎の主な症状は以下の通りです。
・歯ぐきの痛みや腫れ
親知らず周辺の歯ぐきが赤く腫れ、触れると強い痛みを感じることがあります。
・口が開けにくい(開口障害)
炎症が進むと顎の筋肉や関節に影響を及ぼし、口が開けづらくなることがあります。
・膿の排出
智歯周囲に膿が溜まると、口腔内に膿が出てくることがあります。
・発熱やリンパ節の腫れ
炎症が強い場合、発熱や首のリンパ節の腫れを伴うこともあります。
●智歯周囲炎の治療
智歯周囲炎の治療は、症状の程度や親知らずの状態によって異なります。
・消毒と清掃
歯科医院で親知らず周囲を消毒、清掃し、細菌を取り除きます。
・抗生物質の処方
炎症や感染が強い場合には、抗生物質を処方して細菌の増殖を抑えます。痛みが強い場合には、鎮痛剤も処方されます。
・抜歯
親知らずが斜めや横向きに生えており、今後も炎症を繰り返す可能性が高い場合には、抜歯が選択されます。
●まとめ
智歯周囲炎は親知らずの周囲に炎症が起こる疾患で、痛みや腫れ、場合によっては全身に症状を引き起こすことがあります。原因は親知らずの生え方や清掃不足などですが、適切な治療と予防策を講じることで症状を軽減し、再発を防ぐことが可能です。親知らずに違和感や痛みを出たら早めに歯科医院を受診し、適切なケアを受けるようにしましょう。
診療のご予約はお電話やwebにてお待ちしております🦷
歯のクリーニングとホワイトニングの違いとは?
2025年2月1日
こんにちは♬
歯を美しく保つためには、日々の歯磨きだけでなく歯科医院での定期的なケアが欠かせません。その中でも「歯のクリーニング」と「ホワイトニング」は、よく耳にするケア方法です。しかし、両者は目的や効果、処置内容が異なります。
今回は、歯のクリーニングとホワイトニングの違いについてご紹介します🦷

●歯のクリーニングとは?
歯のクリーニングは、歯科医院で行う汚れや歯石の除去を目的とした処置です。主な目的は歯や歯ぐきの健康を維持し、むし歯や歯周病を予防することです。
クリーニングでは専用の器具を使って歯石や歯垢(プラーク)を除去し、歯の表面を研磨してツルツルに仕上げます。この研磨により、汚れが付着しにくくなる効果もあります。また、着色汚れ(ステイン)が取り除かれることで歯本来の自然な色が蘇ることもありますが、歯そのものを白くすることが目的ではありません。
●歯のホワイトニングとは?
一方、ホワイトニングは、歯を白く美しくすることを目的とした審美的な処置です。加齢や飲食習慣(コーヒー、紅茶、赤ワインなど)による歯の黄ばみや色素沈着を改善し、見た目の印象を向上させたい人に向いています。
ホワイトニングには、歯科医院で行う「オフィスホワイトニング」と、自宅で行う「ホームホワイトニング」の2種類があります。オフィスホワイトニングは、歯科医師や歯科衛生士が専用の薬剤と光を使って短時間で歯を白くする方法で、即効性が特徴です。一方、ホームホワイトニングは患者様が専用のマウスピースに薬剤を入れて自宅で使用する方法で、時間はかかりますが効果が長続きする傾向があります。
●クリーニングとホワイトニングの違い
歯のクリーニングとホワイトニングは、目的が大きく異なります。クリーニングは歯石や汚れを取り除き、歯や歯ぐきの健康を保つことを目的とした処置です。見た目の改善は副次的な効果であり、歯本来の色を維持することが中心です。一方、ホワイトニングは歯を本来の色以上に白くすることを目的とし、見た目の美しさを重視した処置です。歯を根本から白くしたい場合は、ホワイトニングを選択するようにしましょう。
●まとめ
歯のクリーニングとホワイトニングは、目的も方法も異なります。歯や歯ぐきの健康を維持するには、歯のクリーニングが重要です。一方で、歯をより白く美しくしたい場合には、ホワイトニングが適しています。ご自身のお口の中の状況にあわせて、適切な処置を受けましょう。診療のご予約はお電話やwebからお待ちしております🦷
歯周病と糖尿病の関係
2025年1月15日
こんにちは♬
歯周病と糖尿病はそれぞれ異なる部位や原因で発生する病気ですが、実はお互いに深い関係があることが明らかになっています。どちらか一方を放置すると、もう一方の症状が悪化する可能性があるため、両方の管理が重要です。
今回は、歯周病と糖尿病の関係についてご紹介します🦷

●糖尿病が歯周病を悪化させる理由
糖尿病になると血糖値が高い状態が続くため、体の免疫力が低下します。その結果歯周病を引き起こす細菌への抵抗力が弱まり、歯茎の炎症が進行しやすくなります。また、血管がダメージを受けることで歯ぐきの血流が悪化し、治癒能力が低下するため、歯周病の治療効果が出にくい場合もあります。
●歯周病が糖尿病を悪化させる理由
一方で、歯周病が進行すると歯ぐきの炎症から炎症性物質(サイトカイン)が全身に広がり、インスリンの働きを阻害します。この影響で血糖値が上昇し、糖尿病の管理が難しくなることがわかっています。
●予防と改善のためにできること
・定期的な歯科検診
歯周病は初期段階では気づきにくい病気です。定期的に歯科検診を受け、早期発見と治療を心がけましょう。
・正しい歯磨きの実践
歯周病予防の基本は、日々の歯磨きです。歯と歯ぐきの境目を意識し、丁寧に磨きます。歯ブラシだけでは十分に汚れを除去できないため、デンタルフロスや歯間ブラシを使用することも大切です。
・糖尿病の管理
血糖値を安定させることは、歯周病の予防にもつながります。適切な食事療法や運動など、医師の指導に従いましょう。
・歯周病治療が糖尿病に与える効果
研究によれば、歯周病を治療することで血糖値が改善することが確認されています。歯周病治療は、糖尿病の管理をサポートする重要な要素と言えるでしょう。
●まとめ
歯周病と糖尿病は相互に影響を与え合う病気です。そのためどちらか一方を管理するだけでなく、両方を同時にケアすることが重要です。日常のケアと定期的な歯科受診を通じて口腔内の健康を保ち、全身の健康につなげましょう。
歯やお口の中のことで心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
診療のご予約はお電話やwebからお待ちしております🦷
インプラントはどのメーカーも同じ?違いを知って選びましょう
2025年1月1日
こんにちは♬
インプラント治療を検討する際、「インプラントはどのメーカーも同じなのでは?」と思う方は少なくありません。しかし、実際にはインプラントメーカーによって特徴や性能が異なり、それが治療の成功率や長期的な満足度に影響を与えることもあります。
今回は、インプラントメーカーの違いや、当院で採用しているストローマン社製インプラントの特徴について詳しく解説します🦷

●インプラントメーカーの違いとは?
インプラントメーカーは世界中に数多く存在し、それぞれが独自の技術や製品ラインを持っています。主に以下の点で違いが見られます。
・材料と品質
インプラントの主な材料はチタンですが、その純度や加工技術によって品質が異なります。一部のメーカーは独自の表面加工技術を採用しており、骨との結合の速さや強度に差が出る場合があります。
・デザイン
インプラントの形状やサイズはメーカーによって異なり、骨の量や状態に応じた適切な選択が求められます。
・信頼性と実績
長年にわたって使用され多くの臨床データを持つメーカーのインプラントは、信頼性が高いとされています。一方、新しいメーカーでは十分なデータが不足している場合があり、長期的な成功率が不明確なこともあります。
・メンテナンス性
インプラント治療後のメンテナンスも重要です。部品の入手のしやすさや、互換性のあるパーツが揃っているかなどもメーカー選びに影響します。
●当院で採用しているストローマン社製インプラントの特徴
当院では、世界的に評価の高いストローマン社製のインプラントを採用しています。ストローマン社はインプラント業界をけん引する企業として知られています。独自の表面加工技術「SLActive®」により骨との結合が従来よりも早く、治療期間の短縮が期待できるインプラントです。世界的メーカーであるため部品の入手もしやすく、将来的なメンテナンスにも対応できることも大きなメリットといえるでしょう。
●まとめ
インプラント治療を成功させるためには、信頼性の高いメーカーのインプラントを使用することが大切です。当院では世界的に評価の高いストローマン社製インプラントを採用し、患者様に高品質で安心できる治療を提供しています。
インプラント治療にご興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。